こんにちは、よっさんです。
某飲食店チェーンでエリアマネージャーをして、現場で働く社員の皆さんがどうやったら楽しく前向きに働けるかを考えています!
自分自身が店長だった時に身につけたノウハウや過去の自分が教えておいて欲しかったことを、まとめて発信しています。
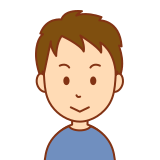
黒板やチョークボードって書くのめんどくさいし、どうしたらいいの?
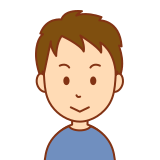
黒板やチョークボードを有効に活用できれば、従業員のモチベーション作り、販促の効果UP、ファン作りと沢山メリットがあるんだ!
飲食店ではよく置いてある手書き黒板・A型看板ですが、落ち着いたときに書き換える、あるいは更新の頻度が少ないと、店舗を訪れるお客さんや、従業員にとって意味の少ないものになってしまいます。
とはいえ、手書きの黒板の構成や更新頻度を自分でイチから考えるのは非常に難しいです。
そこで今回は、手書き黒板を活用すると生まれるメリットとその効力、書き方について解説します。
下記にあてはまる方は、ぜひ最後までご覧下さい。
こんな方に読んで欲しい!
- 会社で手書き黒板を使用している
- 手書き黒板を使用するメリットが分からない
- 手書き黒板の有効活用方法が知りたい!
この記事の内容を意識すると、読む人とって読みやすい日報が迷わずに書けるようになります。
手書き黒板を使用するメリットと基本的な使い方を理解して、店舗の魅力をどんどん発信していきましょう!
手書き黒板を活用するうえで意識するポイントは以下の3点です。
手書き黒板を活用するポイント
- 手書き黒板のメリットと効力を知る
- 販売促進とブランド発信で分けて考える
- 有効活用方法(スケジューリングと育成)
1つずつ解説していきます!
手書き黒板のメリットと効力を知る
どんな道具にも正しい使い方と効力があるように、手書き黒板も正しい使い方と効力を知っておかないと、効果は半減してしまいます。ここでは手書き黒板のメリットと効力を3つ紹介していきます!
- 熱量の高いお客さまに発信が出来る(即効性がある)
- 個店の情報発信が出来る(ファンづくり)
- 手書きならではの味が出る(チェーン店でも個人経営店のような温かみがだせる)
熱量の高いお客さまに発信が出来る(即効性がある)
チェーン店でも個人経営店でも、公式HPやInstagramなどのSNSを活用し、情報発信をされていると思います。しかし、それはどこで見られているでしょうか?お家の中や会社、通勤途中の電車かもしれません。その中で、実際に店舗に来られる方は何割ぐらいいらっしゃるでしょうか?現代社会は情報の渦です。次から次へと魅惑的な情報が発信されるので、お客さまの頭の中に残り続けるのは至難の業と言えます。
手書き黒板のメリット1は、熱量の高いお客さまに発信が出来て、即効性があることです。手書き黒板を置くのは基本的に店内、つまりお客さまが来店されたお客さましか見ないということです。お客さまの熱量を分析すると、店内に来店されたときが一番熱量が高い状態と言えます。つまり、「今から商品を買おう!」という熱量の高いお客さまに限定して発信することが出来、注文前なので一番即効性のある情報発信をすることが出来るのが手書き黒板です。
レジでのオススメももちろん大切ですが、100人に同じ説明をすることなく、同様の効果を見込めることも嬉しいですね。これでレジの従業員はより集中してお客さまとの会話を楽しんでもらえます。頼もしい仲間を1人増やしたイメージでしょうか?
個店の情報発信が出来る(ファンづくり)
チェーン店だと掲示物も本社から送られてくることが多いと思います。どこの店舗に行っても同じ質を担保するのがチェーン店の強みですが、これだと差別化が図りづらい、それも事実です。
手書き黒板のメリットは販売促進に使えるということだけではありません。お店絵の個店ベースの情報発信が出来ることも手書き黒板のメリットです。
例えば、自店舗の周年を伝えて日頃来ていただいているお客さまに感謝を伝えるのも良いかもしれませんね。
手書きならではの味が出る(チェーン店でも個人経営店のような温かみがだせる)
私個人的に手書き黒板の一番のメリットは、同じ内容を書いても書く人によって味が出ることです。100人描いたら100通りの黒板が出来るところです。
あの人みたいになりたいと、まるごとその人の真似をしようとしても、どうしても同じものにはならない。そうやって生まれる違いのことを「個性」といいます。
あの人みたいになりたいと、まるごとその人の真似をしようとしても、どうしても同じものにはならない。そうやって生まれる違いのことを「個性」といいます。
#おあとがよろしいようで
文字のテイスト、色使い、構図など全く同じ人はいないので、みんな違ってみんな良いが体現できます。これは画一的なチェーン店構造の中では、特に強みの部分になります。
販売促進とブランド発信で分けて考える
手書き黒板を有効活用する2つ目のポイントは、「販売促進とブランド発信で分けて考える」です。この2つを詳しく説明していきます!
販売促進は、マーケティング活動の一部であり、顧客の購買意欲を高め、最終的に商品の購入に繋げることを目指します。
ブランド発信とは、企業や個人が、自らのブランド(商品、サービス、または自己自身)の価値や個性を、ターゲットとなる顧客や社会全体に伝えるための活動全般を指します。
この部分を正しく理解するには、ブランドについての理解が必要です。また詳しく説明する機会を設けます。
販売促進について
販売促進とは商品のオススメすることです。メリットは短期的に売上につながること、お客さまがその商品にファンになってもらえることもあります。自店舗でオススメしている商品や季節限定の商品などをオススメすると季節感も出て良いと思います!これは比較的分かりやすいかと思います。
ブランド発信について
ブランド発信を簡略的に説明すると、そのお店や会社のファンになってもらえるような発信をすることです。メリットは短期的な売上には繋がりませんが、ずっとそのお店に来てくれるようになる、来る回数(頻度)が増えるなどがあります。具体的には以下のような発信が出来ます。
- そのお店や会社の生誕を祝う(おかげさまで〇月〇にちで〇周年!)
- 会社や店舗のこだわりを紹介する(知ってました?この商品はここまで手間(こだわり)がかかってます!)
- 地域イベントや労いの言葉を書く
手書き黒板の有効活用方法
手書き黒板のメリットや考え方は理解できたかと思います。ここでは手書き黒板の有効活用方法を具体的に紹介していきます!
- スケジューリング(習慣化)
- PDCAに絡ませる
- 育成に絡ませる
スケジューリング(習慣化)
手書き黒板の唯一にして最大のデメリットは管理が面倒ということです。消して書き直さないといけなかったり、どれくらいの頻度で変更しないといけないかが不明瞭なので、書いたら書きっぱなしでずっと同じ黒板を掲示している人も多いのではないでしょうか?
手書き黒板を上手に活用するにはスケジューリングが大切となってきます。更新頻度ですが、レベルに合わせて変更すると良いです。
- 初心者:1か月に1度
- 中級者:2週間に1回
- 上級者:1週間に1回
更新頻度を決めたら、次は黒板を書く(書いてもらう)時間を捻出します。例えば、毎週月曜日に1時間書く→毎週火曜日に更新など、スケジュールを固定化させることが習慣化の第一歩です。お店が落ち着いたら書くなどですと、ほとんどの場合、いつまで経ってもその時間が取れないまま終わってしまいます。計画と計画を実際に行う時間の確保はセットで行うと良いですよ。習慣化についてはこちらでまとめてますので、お時間あったら覗いてみてください(習慣化はたった21日で出来る!)
PDCAに絡ませる
さて、更新頻度の決定とスケジューリングが出来たら、次のステップです。ここで第2章の販促やブランド発信と絡ませて、PDCAに組み込んでいきましょう。PDCAとはビジネスにおいて使われるフレームワークの1つで具体的には以下のようになります。
PDCA(ピーディーシーエー)とは、Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)の4つの段階を繰り返すことで、業務を継続的に改善していくためのフレームワークです。それぞれの頭文字を取ってPDCAと呼ばれます。
皆さんの店舗にも新商品の販売開始や会社の販促のタイミング、地域イベントなど様々な外的要因があるかと思います。そこに上手くボタンをかけていくようなイメージで手書き黒板の予定も併せていくのです。参考例は以下の通りです。
手書き黒板:8月のスケジュール
手書き黒板:8月のスケジュール(参考例)
1週目(8/1~8/7):新商品の発売日なので、新商品のPR 2週目(8/8~8/14):近隣で花火イベントがあるので、花火イベントの詳細 3週目(8/15~8/21):会社や近隣イベントがないので、自店舗だけで行う販促の取組み 4週目(8/22~8/28):翌月から始まる新商品の告知
「売る」努力よりも「売れる」システムづくり
ひとりひとりに「売る」努力を求めるのではなく、店舗として「売れる」状態を作ってやる
「儲ける」のではなく「儲かる」状態をつくってやる
従業員が特別なことをしなくても努力をしなくても、自然ににそうなるようにしていく
#ニトリ成功の5原則

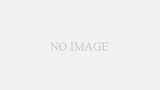
コメント